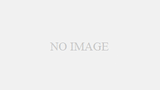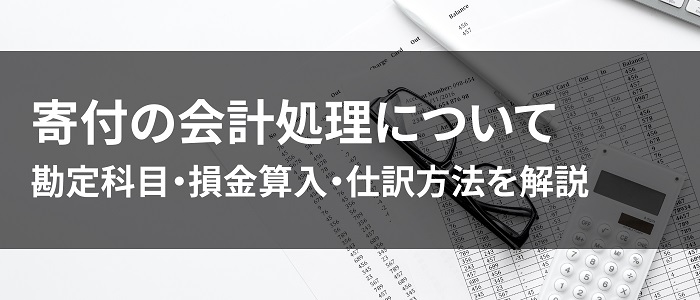
法人・個人事業主の方がNPO法人などに寄付した際、税制の優遇処置を受けるためには、会計処理を行う必要があります。
きっと、手間に感じているものの、正しい寄付の会計処理について知りたいと考えている方は多いのではないでしょうか?
実は、法人と個人事業主で寄付した際の会計処理の方法は異なります。
法人の場合は、「寄付金」という勘定科目で処理するのが一般的。
個人事業主が寄付した場合は、「事業主貸」という勘定科目で会計処理を行う必要があります。
しかも、法人だと寄付を損金として会計処理できるのに対し、個人事業主の方はできません。
ただ、その代わり個人事業主が寄付を行った際、条件を満たしていれば「所得控除」or「税額控除」を受けられます。
寄付の勘定科目だけでなく、法人・個人事業主で損金算入できるかも異なるため注意が必要です。
今回は、そんな寄付の会計処理に関して、法人・個人事業主で違う勘定科目や仕訳方法を解説。
法人であれば知っておくべき損金算入について、また個人事業主の方が受けられる税制の優遇処置について紹介します。
税制の優遇処置を受けるためにも、寄付を行った際の会計処理についてしっかりと理解しておきましょう!
勘定科目は法人・個人事業主で異なる
寄付の勘定科目は、法人・個人事業主で異なります。
法人の場合は「寄付金」、個人事業主の場合は「事業主貸」という勘定科目を用いることがほとんど。
ここでは、会計処理で用いる寄付金と事業主貸について、それぞれわかりやすく解説します。
寄付金について
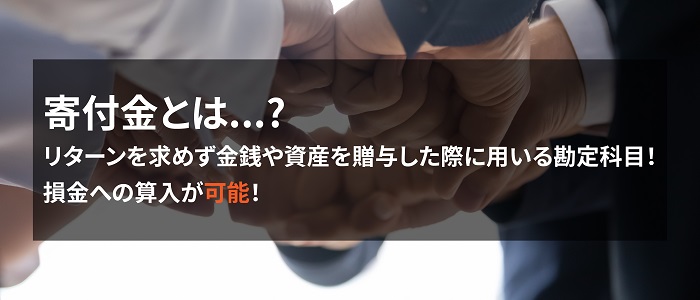
寄付金とは、国や地方自治体、もしくはNPO法人といった団体に対し、リターンを求めず金銭や資産を与えた際に使う勘定科目のことです。
法人が寄付を行った場合は、この勘定科目を用いて会計処理を行う必要があります。
例えば、広告費や福利厚生費などの支出は、寄付金という扱いにはなりません。
反対に、見舞金や拠出金といった名目でも、非営利な団体に金品を贈れば、寄付金として会計処理できます。
この寄付金は、損金として算入することが可能です。
損金算入とは、法人が収入を得るために使った費用を必要経費(損金)として会計処理すること。
ただ、寄付を行う対象によって損金算入の範囲(損金算入限度額)が異なる点には注意してください。
そんな寄付金は、接待費や交際費とは全く違った性質を持っています。
仮に、取引先に対して何らかの支援を行った場合、寄付金として会計処理できません。
これは、取引先への支援が「将来的に売上を上げるための出費」という扱いになるため。
見返りを求めず無償で金品を贈与した際、初めて寄付金という勘定科目を使えるため、取引先への支援は交際費として会計処理しなければいけないのです。
事業主貸について
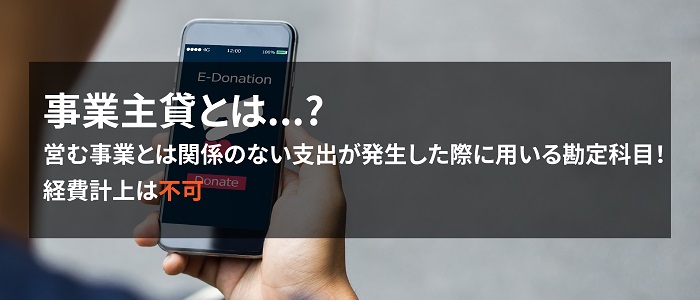
事業主貸とは、個人事業主のみが使える勘定科目のことです。
個人事業主が営む事業とは関係のない支出が発生した際、事業主貸という勘定科目を使用して会計処理を行います。
このことから、「事業とは関係のない支出」である寄付は、事業主貸に該当することがわかると思います。
では、法人が用いる「寄付金」と個人事業主が用いる「事業主貸」で何が異なるかと言うと、損金算入(経費計上)が行えるかどうかです。
上述した通り、寄付金は損金算入が可能。
一方、残念なことに事業主貸は、必要経費として会計処理できません。
ただ、経費計上は行えないものの、個人事業主が寄付を行った際は「所得控除」、もしくは「税額控除」という税制の優遇処置が受けられます。
これらは、認定NPO法人や国などに2,000円以上の寄付を行った場合、いくらかの控除が受けられるというもの。
控除額の計算方法は、国税庁のホームページで確認できるので、ぜひチェックしてみてください。
損金算入に限度額が設けられている理由
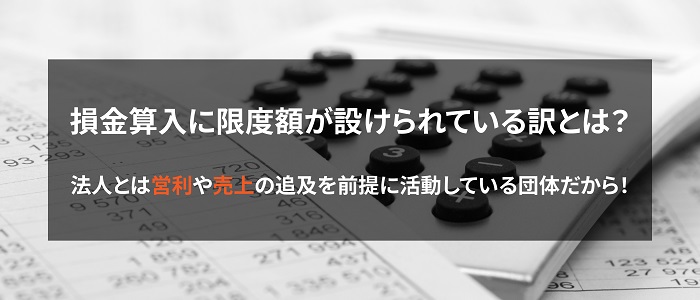
損金として会計処理が行える寄付金。
ただ、損金算入できる金額には、限度額が設けられています。
というのも、法人とは営利や売上の追及を前提に活動している組織だからです。
寄付とは、見返りを求めず金品や資産を贈与すること。
当然ながら、寄付の性質上、直接的な利益が発生することは決してありません。
直接的な利益が発生しないということは、営利や売上の追及を図る上で必要な支出ではないということ。
法人の活動と直接的な関係がなく支出され、必要経費としてみなされないことから、損金として算入できる寄付の金額に限度額が設けられているという訳です。
寄付先で損金として会計処理できる限度額は違う
法人が寄付を行った場合、損金として会計処理できる金額の範囲は、支援先によって違います。
- 国や地方自治体、財務大臣が指定した団体への支援
- 特定公益増進法人への支援
- 一般の支援
これら3つの中でも、国や地方自治体、もしくは財務大臣が指定した団体に対する寄付は、その全額が損金に算入されます。
ただ、国や地方自治体といった組織以外に寄付する場合は、損金として会計処理できる金額に制限が設けられているので注意が必要。
ここからは、特定公益増進法人への支援や一般の支援とな何なのか、またそれぞれの損金算入限度額の計算方法についても紹介します。
特定公益増進法人への支援
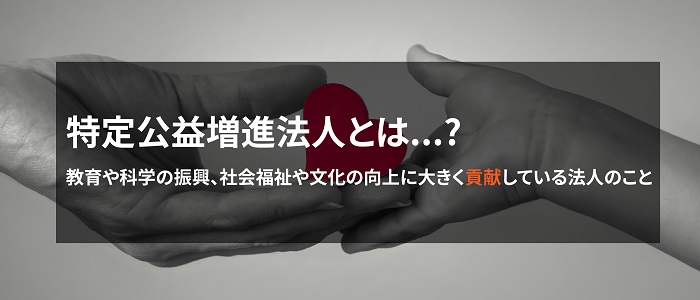
特定公益増進法人とは、教育や科学の振興、社会福祉や文化の向上に大きく貢献している法人のことです。
例を挙げると、日本赤十字社や認定NPO法人などが、この特定公益増進法人に当たります。
仮に、認定NPO法人といった団体に寄付を行った場合、損金として会計処理できる金額の範囲は以下の計算式で求められます。
- [資本金等の額 ×当期の月数/12×3.75/1,000+所得の金額×6.25/100] × 1/2 = 損金算入限度額
例えば、資本金等の額が2,000万円で所得の金額が3,000万円だったとします。
この場合、上記の計算式に当てはめると、損金算入限度額は以下の通りです。
- [2,000万円 ×12/12×3.75/1,000+3,000万円×6.25/100] × 1/2 = 975,000円
この通り、損金として会計処理できる限度額の計算は難しくありません。
もし、認定NPO法人などへの寄付を考えているのなら、上記の計算方法を参考に損金算入限度額を算出してみてください。
一般の支援

国や地方自治体、特定公益増進法人以外への支援に関しては、全て「一般の寄付」として扱います。
この一般の寄付は、国への貢献性が低いため、特定公益増進法人への支援と比べると、損金に算入できる金額が多くありません。
法人が一般の寄付を行った場合、損金として会計処理できる限度額を求める際は、以下の計算式を用います。
- [資本金等の額 ×当期の月数/12×2.5/1,000+所得の金額×2.5/100] × 1/4 = 損金算入限度額
もし、資本金等の額が2,000万円、所得の金額が3,000万円だった場合、これを上の計算式に当てはめると、以下のような結果になります。
- [2,000万円 ×12/12×2.5/1,000+3,000万円×2.5/100] × 1/4 = 200,000円
このように、特定公益増進法人へ寄付した場合と比較して、損金算入限度額が大幅に低いことがわかると思います。
会計処理時の仕訳方法
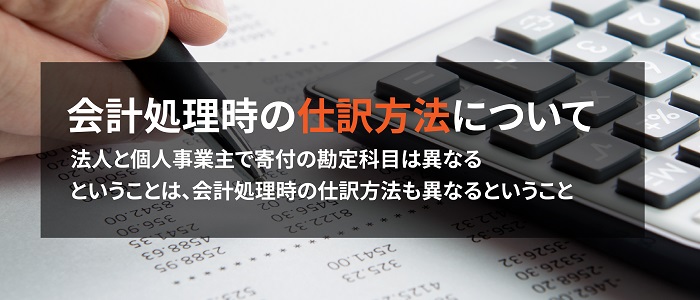
法人・個人事業主によって、寄付の勘定科目が違うということは、会計処理の際の仕訳方法も若干ながら異なるということです。
そこで、ここでは法人・個人事業主で異なる会計処理時の仕訳方法を解説します。
仮に、NPO法人へ現金で10万円の寄付を行ったとすると、会計処理時の仕訳方法は以下の通りです。
法人が寄付を行った場合
| 勘定科目 | 借方 | 勘定科目 | 貸方 |
|---|---|---|---|
| 寄付金 | 100,000 | 現金 | 100,000 |
個人事業主が寄付を行った場合
| 勘定科目 | 借方 | 勘定科目 | 貸方 |
|---|---|---|---|
| 事業主貸 | 100,000 | 現金 | 100,000 |
上記の通り、会計処理時の仕訳方法が異なると言っても、借方の項目が寄付金なのか、事業主貸なのかといった違いしかありません。
そのため、この仕訳方法を押さえておけば、寄付の会計処理に悩むことはないと思います。